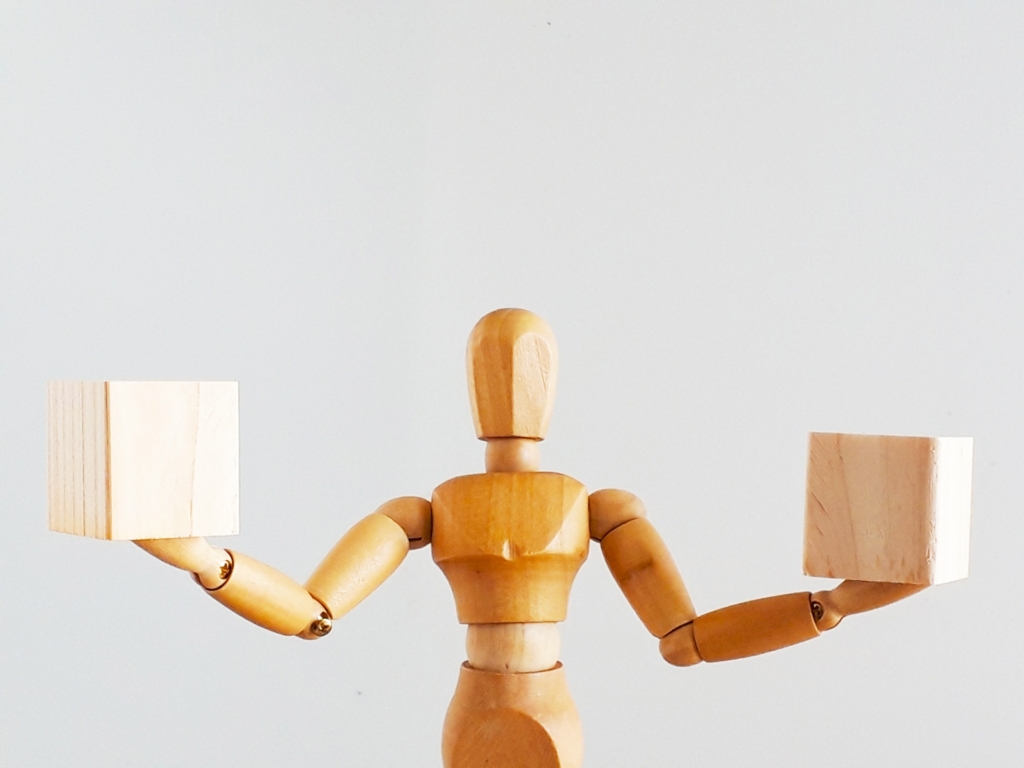
算定基礎届と労働保険の年度更新。これらは企業にとって、毎年ほぼ同時期に対応が求められる手続きですが、目的や対象が異なるため、その違いを正確に理解しないまま処理を進めてしまうと、思わぬ手続き漏れや遅延、最悪の場合、罰金や追徴金が課される可能性があります。本記事では、この二つの手続きの違いを明確に整理し、発生するリスクの対策まで解説します。
算定基礎届(定時決定)とは、従業員の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、毎年1回、標準報酬月額を見直す手続きのことです。標準報酬月額は、4月から6月の報酬を基に算出するため、算定基礎届の対象となる人とならない人がいます。
算定基礎届の対象となる人
・7月1日時点での社会保険の被保険者および70歳以上の被用者
算定基礎届の対象とならない人
・6月1日以降の社会保険加入者
・6月30日以前の退職者
・7月改定の月額変更届を提出する人
・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人
上記を踏まえ、算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までの期間に、管轄の年金事務所、または日本年金機構の事務センターへ提出する必要があります。見直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条1項1号に基づいて、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
労働保険の年度更新とは、前年度に納めた労働保険料を確定保険料として申告・納付し、新年度の労働保険料を概算保険料として申告・納付を行う手続きのことです。労働保険料の算出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日になります。
また、年度更新の対象となる企業は、従業員を雇用しているすべての企業であり、毎年6月1日から7月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までの期間に、管轄の労働基準監督署や労働局、銀行や郵便局などの金融機関へ提出する必要があります。
この手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに、納付すべき保険料・拠出金の10%に当たる追徴金を課される可能性があります。
| 算定基礎届 | 年度更新 | |
|---|---|---|
| 対象 | 社会保険 | 労働保険 |
| 算出期間 | 4月〜6月 | 4/1〜翌年3/31 |
| 提出期間 | 7/1〜7/10 | 6/1〜7/10 |
| 提出先 | 管轄の年金事務所または事務センター | 管轄の労働基準監督署・労働局または銀行・郵便局などの金融機関 |
| ペナルティ | 6ヶ月以下の懲役または50万円の罰金 | 政府による保険料・拠出金額の決定さらに納付すべき保険料・拠出金の10%の追徴金 |
上表は、ここまででお伝えした算定基礎届と年度更新の内容を簡潔にまとめた比較表になります。
また、提出先の行政機関は地域ごとに管轄が異なりますがこちらのページで47都道府県分すべてを確認できます。

算定基礎届と年度更新は、いずれも企業にとって毎年対応が求められる重要な手続きです。処理の内容や対象、提出先が異なるため、正しい知識を持たずに取り組むと、思わぬトラブルを招く可能性があります。ここでは、算定基礎届と年度更新において、企業が特に注意すべき3つのポイントを確認しましょう。
算定基礎届と年度更新は、毎年6〜7月に行うため、手続きのタイミングが重なりやすくなります。そのため、処理を一括で行おうとした際に、対象者や提出先、目的の違いを理解せずに処理してしまい、申告ミスや漏れが発生する可能性が高まります。これにより、結果として従業員の社会保険料や労働保険料の誤徴収・過不足が生じるリスクがあるため、注意が必要です。
4月頃は入社・退職・異動などの手続きが増える時期であり、人事労務担当者にとっては1年の中でも特に忙しい時期です。そんな中、6〜7月に控える算定基礎届や年度更新も待ったなしでやってきます。この手続きはどちらも提出期限を過ぎると、罰金や追徴金といったペナルティが課される可能性があるため、万全の状態で臨みたいところです。
このような繁忙期を乗り切るためにも、スケジュールに余裕を持ち、早めの準備を進めておくことが大切です。
算定基礎届では、対象となる被保険者を正確に把握する必要があります。また、算定基礎届と年度更新はどちらも正しい報酬や賃金の計算が求められます。これらの情報に誤りがあると、結果として誤った保険料の計算や納付に繋がるため、事前に勤怠や給与データの確認・整理をしておくことが求められます。
算定基礎届と年度更新は、提出期限が厳しく、対象者の選定と報酬や賃金の正確な把握が求められるため、社内対応だけではミスが起きやすい業務ということが分かりました。こうしたリスクを未然に防ぎ、手続きを確実かつ効率的に進めるには、社労士の専門的なサポートを活用するのがお勧めです。ここからは、企業が安心してこれらの手続きに対応できるよう、社労士に依頼するメリットを3つ確認していきます。
算定基礎届と年度更新は、毎年ほぼ同時期に対応が求められますが、対象や提出先が異なるため、社内で混同しやすい手続きです。社労士はそれぞれの制度の違いを正確に理解しており、企業の現状に応じた適切な手順を整理・案内してくれます。これにより、二重申請や申告漏れといったリスクを未然に防ぐことができます。
算定基礎届と年度更新は、提出期限が厳しく定められており、遅延による追徴金や行政対応のリスクもあります。しかし、社労士に依頼することで、期限管理を手続きの専門家に任せられるため、企業側は本業に集中しながらも確実に手続きを終えることができます。万が一の対応が必要な場合にも、社労士のサポートが心強い味方となります。
算定基礎届と年度更新では、報酬や賃金の正確な集計や、対象者のチェックは必須ですが、社内だけで勤怠や給与データを確認・整理するには限界があります。しかし、社労士に依頼することで、手続きの要件に基づいて対象者を適切に判定し、企業の勤怠・給与データを正確にチェックしてくれるため、記載漏れや集計ミスなどの実務上のリスクを大幅に減らすことができます。

算定基礎届と年度更新は、どちらも企業が毎年対応しなければならない重要な手続きですが、その目的や対象、提出先が異なるため、正しく理解して対応しなければ手続きの混同や記載ミス、提出遅れなどのリスクが生じます。これらのミスは、罰金や追徴金といったペナルティだけでなく、従業員や行政機関からの信頼を損なう結果にもなりかねません。
こういったリスクを回避し、確実かつ効率的に対応するためには、社会保険や労働保険の専門知識を持つ社労士のサポートを活用することが効果的です。社労士は、手続きごとの違いを明確に整理し、期限管理や記載内容の正確性までを一括してサポートしてくれるため、企業の実務負担を大きく軽減しながら、安心して手続きを完了させることができます。煩雑な手続きをミスなく進めるためにも、早めの準備とともに、信頼できる専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
労務の灯台 編集部
ハタラクデザイン合同会社が運営するWebメディア「労務の灯台」編集部。様々な角度から社労士の関連情報をお届けすることで、自社の価値観に合った社労士を見つけてもらいたいと奮闘中。