
人手不足を解消する新たな手段として、近年「スポットワーク」が注目されています。しかし、単発での雇用だからといって、労働に関するルールが適用されないわけではありません。むしろ、スポットワークだからこそ注意すべきポイントがあります。 本記事では、スポットワークを導入する際に企業が押さえておくべき注意点を【導入前】【導入時】【導入後】の3つの段階に分けて解説します。また、各段階で社労士を活用するメリットについても触れていますので、スポットワークの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
スポットワークは、短時間・単発で働く就業スタイルです。多くの場合、スポットワーク仲介業者が提供するマッチングサービスに企業が求人を登録し、それに求職者が応募して雇用が成立します。従来のアルバイトよりも「必要なときだけ」雇用できるのが特徴で、繁忙期やイベント時など、一時的に人手が欲しい場面で多く利用されています。
【スポットワークが活用されやすい職種】
☑ 飲食業(ホール・キッチン補助)
☑ 物流・倉庫業(仕分け、梱包)
☑ 小売・販売(レジ・品出し)
☑ イベント運営(受付や設営)
☑ 事務系(データ入力・コールセンター)など
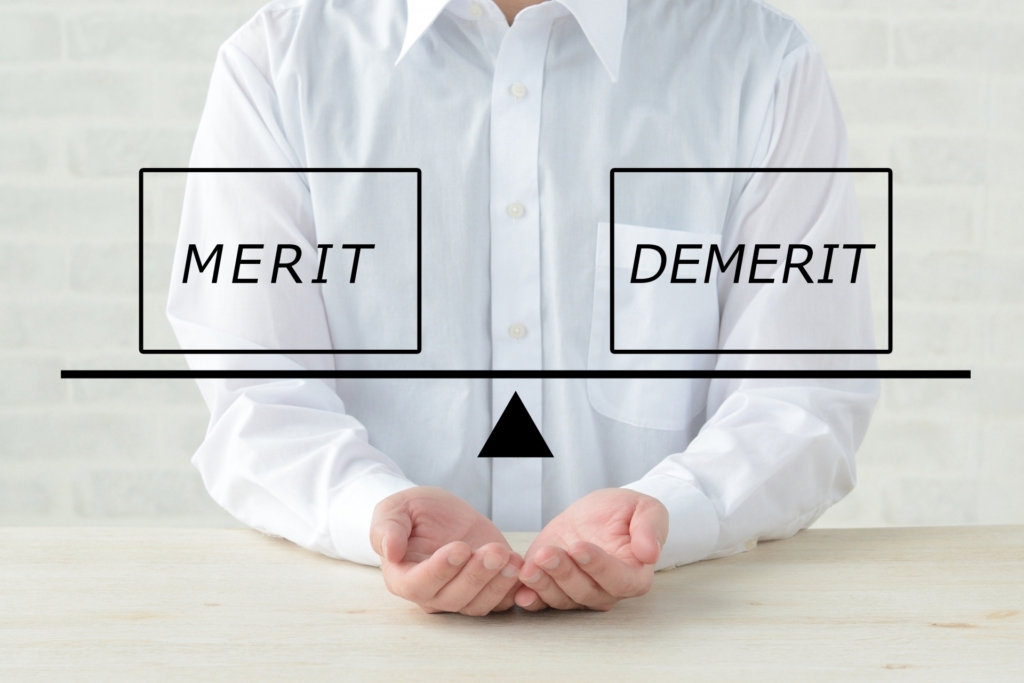
スポットワークは、人手不足の解消や業務効率化に役立つ様々なメリットがある一方で、デメリットもあります。自社の業務内容や求める人材の質を踏まえた上で、導入を検討することが大切です。
◯メリット
・働く期間や時間が短いため、必要なときだけ人材を確保できる
・シフト調整がしやすく、急な繁忙期にも対応しやすい
・長期雇用に比べ人件費を抑えられる
・求めるスキルや条件に合った人材を集めやすい
・採用にかかる手続きが簡単
・長期雇用に切り替えることも可能
◯デメリット
・雇用契約を結ぶ以上、労働基準法などの法令を遵守する必要があり、管理や責任が発生する
・単発ゆえにミスマッチが起こる可能性がある
・人材の質にばらつきがあり、業務水準が安定しにくい
・直前のキャンセルリスクがある
・長期的に安定した人材を確保しにくい

スポットワークを導入する際は、段階ごとに確認しておきたい注意点があります。ここではまず、「導入前」の段階で企業が特に気をつけるべきポイントを見ていきましょう。
スポットワークを導入する際は、依頼する業務内容を事前に決めておくことが大切です。業務内容が曖昧だと、現場でのトラブルやミスマッチの原因になりかねません。
例えば、以下のように具体的に仕事内容を決めておきましょう。
・飲食店ホール(注文取り・配膳・片付け)
・倉庫ピッキング(商品集め・梱包作業)
・イベント設営(会場の備品運び・撤去)
・データ入力(顧客情報・アンケート入力)
また、未経験でも問題ないのか、ある程度の経験が必要なのかなど、必要な「スキル」や「条件」も事前に確認しておくことが重要です。
スポットワークを導入する前に、自社に就業規則があるかどうかを確認しましょう。常時10人以上の労働者を雇用している場合、就業規則の作成は法律で義務づけられています。正社員やアルバイト用の規則があれば、そのままスポットワーカーにも適用されるため、内容をしっかり見直してください。必要に応じて「スポットワーク専用」の就業規則を作るのもおすすめです。
さらに、初めて現場に入る人でも一定の水準で仕事ができるよう、イラストや写真を使った「マニュアル」も用意しておきましょう。こうすることで品質にバラつきが出にくくなり、作業もスムーズに進みます。
スポットワークを導入する際、必ずしも新たに就業規則を作る必要はありません。ただし、既存の就業規則をそのまま適用すると、スポットワーカーの働き方に合わず、思わぬトラブルや余計なコストを招くリスクがあります。
・正社員向けの割増賃金や手当の規程が適用され、予定外の支払いが発生する
・制服や服装・メイクの基準が曖昧で、サービス品質に影響が出る
・安全衛生ルールが不十分で、事故やトラブルが生じる
上記のようなリスクを避けるためには、導入前に「社労士」へ相談し、就業規則や職場ルールを整備しておくことが大切です。これにより、安心して契約を結べるだけでなく、不要なトラブルも未然に防げます。

次に、スポットワークを実際に導入する段階で注意すべきポイントを確認していきましょう。
スポットワークは一時的な働き方ですが、法律上は通常のアルバイトと同じく、事業主と労働者の間に労働契約が成立します。そのため事業主は、労働基準法をはじめとする法律を守り、賃金の支払いや労働時間の管理などについて責任を負わなければなりません。なお、スポットワークを仲介するサービスがあっても、労働契約を結ぶのはあくまで「事業主と労働者」です。この点には特に注意しましょう。
労働契約は、原則、使用者と労働者の合意により成立します。
【労働契約法第6条(労働契約の成立)】
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
しかし、スポットワークでは通常の採用のように面接を行わず、アプリ上で応募と承諾が完結するケースがほとんどです。そのため、十分に内容を確認し合う機会がないまま仕事が始まることになります。
では、いつ合意があったとみなされるのでしょうか。一般的には、スポットワーカーが応募し、企業がこれを承諾した時点で労働契約が成立するものと考えられます。つまり、この時点から、企業は賃金の支払いや労働時間の管理、安全への配慮など、法律に基づく責任を負う可能性があるのです。
労働契約を結ぶ以上、スポットワーカーにも他の従業員と同様に労働基準法が適用されます。つまり、採用時には労働条件をきちんと明示し、「労働条件通知書」を交付しなければなりません。
労働条件通知書は書面で交付するのが原則です。書面で明示しておくことで、後から「言った・言わない」といったトラブルを防ぐことができます。なお、多くのスポットワーク仲介事業者が交付を代行していますが、交付義務そのものは事業主にあります。必ず交付状況を確認し、未交付であれば自社で対応するようにしましょう。
スポットワーカーを受け入れる際には、「雇入時の安全衛生教育」を必ず実施しましょう。現場に不慣れなスポットワーカーは、どうしても事故やトラブルのリスクが高くなります。
安全衛生教育の主な内容は、以下のとおりです。
・機械や原材料の危険性、有害性、およびその取り扱い方法
・安全装置や保護具の性能と使い方
・作業手順や作業開始時の点検方法
・業務上発生しうる疾病の原因と予防
・整理整頓および清潔の保持
・事故時の応急措置や退避方法
・その他業務に必要な安全衛生事項
加えて、職場ごとのルールもきちんと周知しましょう。服装や持ち込み禁止物、作業エリアの立ち入り制限など、細かなルールまで説明しておくことで、トラブルや事故を防ぐことができます。
本来、スポットワークを導入する際は専用の就業規則を作るのが理想です。しかし手間やコストがかかるため、就業規則を作らずに進める企業も少なくありません。その場合、「労働条件通知書」が実質的に唯一のルールになります。多くの事業主はネットのテンプレートをそのまま使いますが、これでは余計な規程を盛り込みすぎたり、逆に重要な点が曖昧になったりするリスクがあります。
こうした不備があると、いざトラブルになったとき「書面に書かれていることがすべて」とされ、「そんなつもりではなかった」という言い分は通りません。だからこそ、労働条件通知書を作成する段階から社労士に相談し、自社の実情を反映した内容にしておくことが大切です。これによりトラブルを未然に防げるだけでなく、スポットワーカーにも安心して気持ちよく働いてもらえるでしょう。

では、スポットワークを導入した後は、どのような点に注意を払うべきなのでしょうか。ここでは運用段階で特に気をつけたいポイントを解説します。
スポットワーカーを雇用する場合も、労働時間や賃金は通常の従業員と同様に正確に管理する必要があります。
特に注意したいポイントは次のとおりです。
・制服への着替えなど業務に関連する作業時間は労働時間に含まれる
・現場での待機時間も労働時間に該当する
・時間外や深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合は、割増賃金や深夜手当を支払う
また、労働条件通知書で示した賃金を事業主の都合で減額したり、約束した交通費を支払わなかったりすることは、労働基準法違反にあたるため避けましょう。
スポットワークを予定していても、以下のようなケースは十分に起こり得ます。
・想定より業務量が少なくなり、早帰りを命じた
・工場設備の故障などで、これ以上業務が続けられず帰宅させた
このように会社都合でスポットワーカーを休業または早上がりさせる場合は、休業手当の支払いが必要です。
具体的には、労働基準法第26条において「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者はその期間中、平均賃金の100分の60以上を支払わなければならない」と定められています。なお、スポットワーカー本人が自ら希望して早上がりする場合は、休業手当の支払いは不要です。
スポットワーカーであっても、通勤途中や業務開始から終了までに発生したけがや病気は、通常の従業員と同様に労災保険の対象となります。
例えば、飲食店でスポットワーカーがやけどをした場合は、事業主として労災の手続きを行わなければなりません。この際のポイントは、病院を受診させるときに健康保険証やマイナ保険証、資格確認書を使わせないことです。診察の際には必ず「労災である」と伝えるよう、本人に指示しましょう。
スポットワーク導入後は、通常よりもハラスメントが表面化しにくくなるため、的確なハラスメント対策が求められます。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、2022年4月からは企業規模を問わず、ハラスメント相談窓口の設置がすべての企業に義務化されました。また、相談窓口の存在を従業員に周知することも忘れないようにしましょう。
前述したように、スポットワーク導入後は、労働時間の管理やハラスメント対策など、細やかな労務管理が求められます。
例えば、スポットワーカーが他の職場でも働いている場合、労働時間を合算して割増賃金が発生するケースもあります。もっとも、企業側がその事実を知らなかった場合に支払い不要とされた判例もありますが、こうした労務管理には正確な知識が必要とされます。情報を自社で調べて対応するには相応の時間と労力がかかります。しかし、社労士に任せることで、法令に則った対応を効率的に進められ、企業は本業に専念できる余力が生まれるでしょう。
また、ハラスメント対策は企業規模にかかわらず義務づけられています。制度整備が不十分なままだと、従業員の不満やトラブルの火種になりかねません。社労士に依頼すれば、自社に適した相談窓口の設置や対応ルールの策定を提供してもらえます。その結果、ハラスメントによる賠償リスクの回避はもちろん、人材の定着や組織力の強化にもつながるでしょう。

スポットワークの導入は柔軟な人材確保手段として非常に有効ですが、導入・運用には法令遵守や労務管理といった多くの注意点が存在します。導入前の就業規則の整備、導入時の契約手続きや労働条件通知、そして導入後の労働時間管理やハラスメント対策に至るまで、いずれの段階でも専門的な判断が求められる場面は多岐にわたります。
こうした課題を社内のみで対応しようとすると、見落としやトラブルのリスクが高まり、結果として余計なコストや信用低下を招く恐れもあります。このような対策方法として、スポットワーク導入を検討している企業は、労働法に精通した社労士のサポートを受けることが効果的です。自社に最適な制度設計やルール整備を行い、安心・安全なスポットワーク運用を実現するためにも、社労士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

webライター 髙橋 朋子
大学卒業後、倉庫会社の人事課で約8年間勤務。労務手続きや採用活動を主に担当。
子育てとの両立に限界を感じ、webライターに転身しました。今は2児の育児と仕事に奮闘中。趣味は読書とランニング。令和2年度 社会保険労務士資格合格済み。